〈本〉による〈革命〉の夜話。失われた「文学」を憂いつつ、美しい文体で「文学」の本来の意味を取り戻す方法。そしてその繰り返し。

希望が持てるって本当にいいことだ
佐々木中氏の『切りとれ、あの祈る手を』は、2010年もっとも熱くなったテキストだ。筆者が学生時代から情報をシャットアウトして生活しているという告白に始まり、「命をかけて〈本〉を読み/書きすることのみが〈革命〉である」という高らかな宣言へと至る。これは研究対象への深い洞察に導かれた答えである。そして筆者本人の〈本〉に対する姿勢でもある。
すぐに『夜戦と永遠』を読み始めたが、もっとラカンとフーコーを深く理解してからにしようと、読む手を止めた。『九夏前夜』は小説なので見送った。そうした矢先、書店で新刊の『足ふみ留めて – アナレクタ 1』を見つけてしまった。ハルキストならぬアタリストな人は結構いそうだし、この世界観と文体に共感できるなら、いろんなことに希望が持てる。今の彼が圧倒的にオルタナティブな存在であることは疑いようがない。
そして今回は、フーコーの可能性を説いたテキストでいきなりぶっ飛ばされた。

われわれはもう長く見すぎた、目を逸らすのはもうやめよう
少し長くなるが、引用したい。
真理に到達する条件として知そのものしか求めない「哲学(フィロゾフィー)」と、身体的な訓練、道徳的な修養をその要件とする「霊性(スピリチュアリテ)」のあいだの、それ自体は常識的な区別を強調しつつ、後はあの高名な「自己への配慮」「生存の美学」を導出していった。自ら語っている通り、フーコーはそれに「魅惑されて」いた。しかしその検証の途中で、彼は様々なことを指摘しなくてはならなくなる。いわく、自己への配慮は、出世のための親類縁者の「コネクション」の切っ掛けとなるものだった。また、それは有閑階級の気取った「流行」にすぎないものだった。それに、掟なき、主人なき、「導者(グル)」なき訓練などということは幻想であって、実際は一種の教団において自己への配慮は「指導」されていた、と。
(中略)
これは出世のための「コネをゲット」するための「自己啓発」である。「セレブたち」の「ヨガ」や「ピラティス」である。卑小なるカルト教団の長への服従のもとにある「修行」である。だから、こうしたものに縋(すが)るのはもうやめなくてはならない。威勢よく政治や正義や倫理を語ってみせる論旨が、最後に「僕たちのスタイル」や「抵抗の美学」などという駄弁に頽(くずお)れていくのを、われわれはもう長く見すぎた。自己への配慮、生存の美学は、抵抗や革命を何ら保証しない。目を逸らすのはもうやめよう。くりかえす。このことはフーコー自身が語っていることである。
佐々木中『足ふみ留めて – アナレクタ 1』 – 「生存の美学」の此岸で
これは『夜戦と永遠』の終わりに近いあたりでも使われたテキストであった。
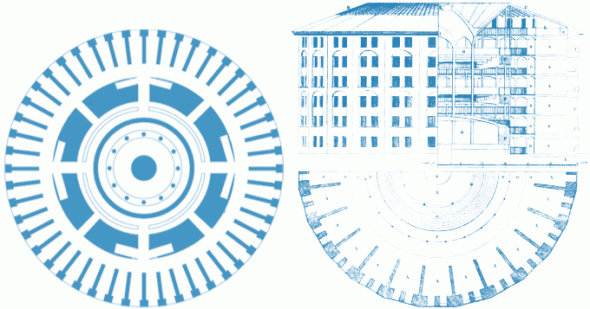
すべては情報だなどと、なんと古くさい考え方だ
『切りとれ、あの祈る手を』では、マネジメント原理主義批判にも言及している。
ジル・ドゥルーズの力強い言葉がありますね。「堕落した情報があるのではなく、情報それ自体が堕落なのだ」と。ハイデガーも、「情報」とは「命令」という意味だと言っている。そうです。皆、命令を聞き逃していないかという恐怖に突き動かされているのです。(中略)命令に従ってさえいれば、自分が正しいと思い込める訳ですから。自分は間違っていないと思い込める訳ですから。
佐々木中『切りとれ、あの祈る手を—〈本〉と〈革命〉をめぐる五つの夜話』
この指摘はルジャンドルへの言及により、情報革命の新仮説につながっていく。十二世紀の中世解釈者革命における「法」の読み直し/「テキスト」の書き直しによって、「法」の索引がつくられ、「法」文が検索できるようになり、人間を統治する道具が「情報」のみになった、という仮説である。しかし「テキスト」本来の「文学」的な思考のダンスによって、ポストモダンとは違う地平に辿り着くことができると筆者は強調する。
「すべて」が情報である、だなんて、もう800年も延々やっているわけですね。それがみんな新しいと思っているわけでしょう。滑稽です。ここから何も変化はなく、ここから脱出する術はない、と。そんなことは無い。ありえない。創り出したのが人間なら、われわれ人間はそこから抜け出すことだって出来るはずだ。必ず、必ずね。
佐々木中『切りとれ、あの祈る手を—〈本〉と〈革命〉をめぐる五つの夜話』

何も終わらない、何も
参照され、解釈されつづける〈本〉。繰り返される「テキスト」。そして「文学」。反復の熱力学。
この世界そのものがマルキシズムの限界を証明してると言われても、マルクスのテキストは今も熱気を帯びている。音楽で意識の〈革命〉が起きると本気で思っていた、ヒッピーたちの熱気を想像してもいい。反復するビートが熱く体を巡るダンスでもいい。あのあまりに合理的で冷たい設計図に行き着く前に。そして、これはただの自分の熱気である。
読むこと/書くことのはじまりの始まりで、われわれは少し勘ぐり深くなっている。誰も全てについて全てわかってないし、何かについて全てわかることなどありえないのだ。筆者はそれを終末思想であると批判し、何度もこう繰り返す。
「何も終わらない、何も」と。
- Amazon: 佐々木中『足ふみ留めて – アナレクタ 1』
- 佐々木中 × いとうせいこう「Back 2 Back」
いとうせいこうと佐々木中による東日本大震災へのチャリティ連作小説


