想像のラカン派をつくるための試み。佐々木中のラカン講義、第4のノート。
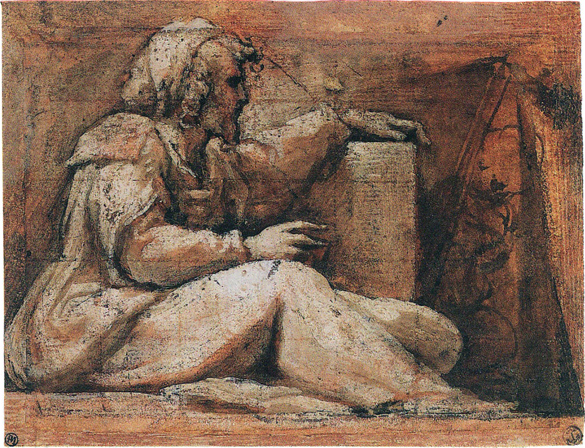
法/権利/法権利=「法」
ヨーロッパの思想家には、感性/悟性を取り扱う観念論や認識論から出発して、最終的に道徳論や国家論そして「法」に辿り着くという伝統がある。
「法」は英語の”law”、フランス語の”loi”が訳されたものであるが、同じように英語の”right”、フランス語の”droit”も「法」と訳される。例えばヘーゲルの『法の哲学』の「法」も、元はドイツ語の”recht”、つまり”right”である。
“right”の訳語として妥当なのは、果たして「権利」という言葉だろうか?そもそも”right”という言葉に「利」の意味があるだろうか?「権利」という文字の前後を入れ換えると「利権」になってしまう。「権利」という言葉には、そんな危うさが付きまとっている。
最近はよく「法権利」という造語が充てられるが、違和感があると不評である。過去に「権理」という言葉に置き換える試みもあったが、定着しなかった。こうして長い間、”right”=「権利」は巧妙に隠蔽されている。
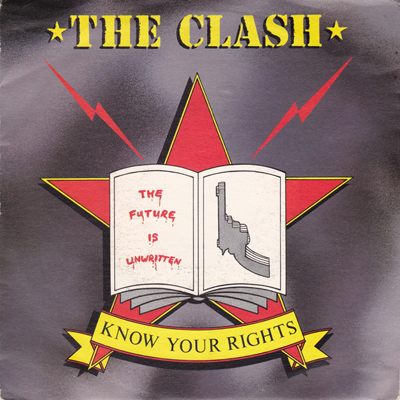
The Clash / Know Your Rights (1982)
書き始めること、消すこと、書くのを終えること
「権利」の「権」とは、英語で”authority”、ラテン語で”auctoritate”、「権威」にあたる言葉である。また”author-ity”の”author”とは、英語でもラテン語でも「著者」の意味である。テキストを書く者のことである。

テキストを書くこと。それは自分で書いたことを消すことができる、次の一行で書いたことを否定できるということである。パブロ・ピカソが同じ作品を何度も塗りなおしたような、アルベルト・ジャコメッティが何度も自分の作品を作っては壊したような、一つの芸術作品にいくつものバージョンがある様子に似ている。
テキストを書くこと。それはたまたま書いたテキストによって、次に書くものが決まっていく、そんな過程でもある。偶然描いた線によって、次に描くものの必然が生まれるように、自分で書いたものによって自分自身を追い詰めていく作業である。
しかし、テキストを書くことを終え、完成としたと宣言し公開した途端、”author”となる。偶然の書き手は「著者」または「作者」となり、責任という必然に閉じ込められる。ヴァレリー曰く、「作品が完成したということは、途中で諦めたことである」。ここで止めようと思い立つこと。書くことは、始まりも終わりも、偶然性に包まれている。
ラカン派の「権威」となったラカンの理論は、ついにフランス政府公認の理論とされた。その理論の偶然性が、さらに大きな「権威」によって必然に変わっていったことが原因となり、やがて多くの人がラカンの元を去った。
ラカン、その「権力」の理論
「権威」(”authority”)とは、何かを諦めることであったが、「権力」(”power”)という言葉にそのような意味は含まれていない。「権力」のフランス語である”pouvoir”の”pouv”とは、「何かができる」「可能性がある」という意味である。
「権威」から「権力」へ。ある可能性を諦め、別の新しい可能性を手に入れること。ある「何か」ではなく、その「何か」ではないという烙印を押されて初めて、われわれは別の「何か」になる。
ラカンに準えれば、鏡を見て「これが私である」と思った瞬間に、「権力」は発生する。姿が与えられ、名が与えられることによって、ある可能性が開かれる。「欲望」を断たれ、「去勢」された結果として、「欲望」が再設定される。これは「他者」=「社会」の限定によるものであった。「欠如」の、「穴」の、「否定性」の理論家と呼ばれたラカンの理論とは、「権力」の理論と言える。
「権力」の作用とは血塗られたものであり、われわれはいつもある種の「権力」に晒され、「権力」に抗する存在である。もちろんここでの「権力」という意味を、国家権力、司法権力などの主権的で抑圧的なものに取り違えてはいけない。フーコーも、「ある事柄をみんなが知っているということは権力に晒されていることになる」が、「権力そのものは悪ではない」と言っている。

「権力」のある場所
ルジャンドルが「性的なものに絡まない権力はない」と言うように、「権力」がある場所にはいつも性の幻想(ファンタスム)がある。またフーコーは、1976年のコレージュ・ド・フランス講義の最終日において、「性」は、「権力」が規律の目標とする個人の「身体」と、「身体」の再生産を調整する「社会」が交差する場所にある、と説明している。その同じ年の終わりに刊行された『性の歴史』の第一巻である『知への意志』では、この様子がさらに詳しく描写されている。
性と快楽に対する権力の関係は細分化し、多様化し、身体の上を歩きまわり、行動の内部に侵入する。そしてこのような権力の突出部に、散乱し、特定の年齢や場所や好みや行為のタイプに標本をピンで留めるようにして固定された性的欲望が、定着するのである。権力の拡大による性的欲望の増殖であり、これら特定領域の性的欲望の一つ一つが介入の表面を提出している権力というものの増加である。
ミシェル・フーコー『知への意志(性の歴史 I)』
つまり「権力」は「社会」のどこかに発生するもののではなく、つねに「社会」の内部にあり、個人の「身体」を貫いているものなのである。
権力が「つねにすでにそこにある」ということ、人は決してそれの「外部」にはいないということ、権力と絶縁した人々が自由に駆け回っているような「余白」は存在しないということ、こうしたことには間違いがないように思われる。
『ミシェル・フーコー思考集成〈6〉セクシュアリテ・真理 1976-1977』-「権力と戦略」
だから「社会」の「外部」に向かうことは、ラディカルな態度ではない。「社会」の内/外といった、実体のないものを実体化して考えることを止めなければならない。他にも、秩序(ノモス)/無秩序(カオス)、国家/個人、繁殖性/不毛性、生産/非生産。こうした二分法の構図を避けなければならない。「秩序」の外にあるのは「無秩序」ではなく、また別の「秩序」である。「国家」から逃れるために国境を越えたところで、また別の「国家」に流れ着く。
これは精神(esprit)/身体(corps)の対立の構図も同じである。「身体」は決して精神分析の敵ではない。鏡を見ることで、「対象a」の存在、その場所でも、時間でもない、その無限の動きに気づく。そしてまだ姿を与えられていない「肉」(materiality)に「身体」が与えられ、そこに「精神」が生成される。そこが「権力」のある場所、可能性が見出される場所である。
- Amazon: ミシェル・フーコー『知への意志(性の歴史 I)』


